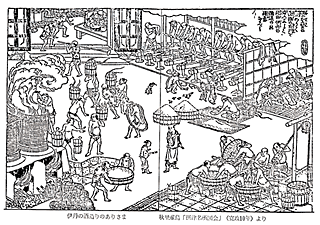
伊丹の酒造りのありさま 秋里離島「摂津名所図会」(寛政10年)より

江戸積銘酒番付 伊丹酒の全盛時代
(伊丹武内利兵衛氏所蔵)より |
徳川時代の伊丹酒に就ては、聖心女子大教授岡田利兵衛氏の好著「徳川中葉の伊丹酒」に詳述されているので、同書を借りて編述することにした。
同書冒頭に、伊丹酒という言葉が巳に野暮であって、その頃の通人は伊丹と言えば酒のことを直感したものである。つまり伊丹は町の名であって同時に酒の代名詞となっていたと書かれているが、編者も先年札幌在学中に千島エトロフ島旅行の際同島を横断、トシモイ湖畔の木挽小屋で木樵(きこり)から問われて、伊丹から来たと答えたら即座にアヽ名高い”伊丹樽”の出る所ですねと言われて、遥かに遠い郷土伊丹の酒を知っていてくれて驚き且つ嬉しかった。
(以下岡田利兵衛氏「徳川中葉の伊丹酒」から抜萃転載)
清酒醸造業の起源に関しては諸説あるが、発祥地が北摂の地であり、徳川時代に到って発展の機運に向ったことは確かである。その醸造業が寛永から慶安に入って伊丹で盛大に行われた当時の古記録(慶安五年三月の鹿島屋理右衛門宛酒樽積上)によると、摂州伊丹の酒家豊島屋叉三郎なる者の店が江戸瀬戸物町にあったことが窺われる。
斯くて寛文に進み、元年近衛家が伊丹の領主となるや、斯業は断然活気を呈したのである。即ち近衛家はその郷土の特産品である伊丹酒に特別の庇護を加えた。伊丹で造られた酒は、「近衛殿御家領摂州川辺郡伊丹郷」なる旗印を堂々さしかざして江戸に京都に天下に濶歩した、何しろ近衛家は五摂家の随一である。何人の追随をも許さない、その近衛家の名に於て乗り込んだのであるから、他の何郷の酒よりも優先権を与えられていたものである。
実に近衛家は伊丹酒の恩人である。だから売れる、売れる、酒さえ造っておれば黄金が湧いて蔵が殖えたという。
彼の朱廸の酒徳領(風俗文選巻十)に「伊丹鴻池の酒蔵、日々に身を潤し月々に屋を潤す。…きのうまでは下部の藤次といえる者もきょうは何がし町の名主宿老の列につらなり、小売諸酒の細もとでも白壁をならべ大釜の煙り絶ゆる時なし…皆飲ぬけの金銀にて三葉四葉の酒蔵とはなれるなり」と書いている。
最初は僅かに一荷を肩にして遙々江戸に售ったとさえ言われる伝説のある清酒が、この頃は跳躍的に発展して夥しく船で江戸積されている。実に二十萬樽から二十五萬樽に及んで江戸へ送り出されているのであるから驚かされる。
これらの酒は、伊丹の下市場叉は雲正下から高瀬舟に積出し、猪名川に出でて神崎の浜へ送り、ここの問屋から海路江戸へ廻送されていた。(この猪名川の舟楫杵はなかなかやかましいものであった)航海中は随分危険もともない悲劇も起ったらしく、これ等航海の安全を期するには、金比羅宮を祀るに限るというわけであったろう。
天和二年に野々宮寺(金剛院といい野の宮別当を司る)境内に金比羅宮を勧請している。(野々宮寺記による)それほどの酒家の念願も至らぬものがあったものか、有岡年代秘記(古野将盈編)宝永六年の條(金比羅宮勧請より十八年後)に次の如き記事が載せられている。
「七月熊野浦にて六百艘破船酒積合五十余艘酒荷物二萬五千駄と云」
この中には伊丹酒が多分に含まれておったことと思われる。然らば一体この頃伊丹でどれ位の酒が製造されていたか、これを記述する前に考査したい事は、次々に発せられた造石制限令のことであるが、「有岡年代秘記」によると寛文六年から延法、元祿、正徳、享保と色々の造石制限令が発せられている。この仰付に背いて製造した者は、或はその分だけ召し上げられたり過怠金をとられたりしているから相当厳重な制限であったと思われる。そしてその方法が石数の何分の一と定めるのと、当座酒を禁ずるのと二様あったことが知れる。
これ等制限は何が急に行われたか、或は近頃行われるような製造過剰を防止する為の制限の意味もあったかも知れない。然し上記の享保(十八年正月)の制限が米価石につき百三十匁に騰貴した為に発せられたり、後年の天明七年の制限が同じく米価二百三十匁に騰った為に仰付けられていたり、延宝七年仰付が白米の使用高を申告せしめている等、米政策を第一とした時代のことであるから、恐らく米価調節食糧問題等に起因する制限であった事が推知される。換言すれば、酒家で費やす米が直接米価に影響するほど、それほど多量に酒が醸造されたことを想像するに難くない。
さてこの頃の造石高を知るに二つの貴重な資料がある。
 |
正徳五年乙未十一月酒造白米本株帖 |
一帖 |
 |
正徳五年乙未十二月酒株之寄帖 |
一帖 |
この二つは姉妹編である、前者は(表紙、裏共合せて紙数十八枚あり)元祿十年調査の酒株を申告せしめたものであるが、これによると
| 元祿十五年御改之株 |
|
| |
|
一、白米四百拾壱石九斗 |
多田屋 清右衛門 |
| 右之酒株家蔵共油屋平九郎借請酒造仕候 |
| |
右同断 |
|
| |
|
一、同弐千百弐拾壱石四斗四升九合六勺 |
木綿屋 七郎右衛門 |
| |
右同断 |
|
| |
|
一、同二千四百八拾八石八斗 |
一文字屋 作右衛門 |
を第一頁に記載し(以下省略)
最後に
| |
惣白米 |
株数八拾壱 |
|
| |
|
同八万千七百七石参斗弐合八勺 |
|
| 右之通少茂相違無御座候 以上 |
| |
正徳五乙未歳霜月 |
惣宿老 上嶋八良兵衛 |
| |
|
惣宿老 小西 与市良 |
| |
藤林 求馬殿 |
|
| |
岡本 帯刀様 |
|
| |
中村 一学様 |
|
と記し尚奥に酒家中惣連判の上、公儀申付の通り元祿十年の三ヶ一制限令を相違無く守る可く誓約している。
後者は(中味三十三枚外に数枚の余白を残している)右の十一月の申告に基き、所謂正徳五年の仰付を実行すべくその制限による石数を各自株数に就いて決定申告の上、違背なきことを薬屋新右衛門以下六十九名の酒造家に誓わしめたものである。
この二つの資料により、当時の造石高を明確に知ることが出来る。即ち前者によると、元祿十五年改めの使用白米高は驚くべし実に合計八萬千七百七石参斗弐合八勺の多額にのぼっている。之を清酒に見積もって大略十二萬余石の酒が出来ていたのである。
尤もこの内四拾八株白米六萬三千余石は、元祿十年当時の伊丹酒家であり、三拾三株白米壱萬八千石分は、正徳元年の近衛家御加増により伊丹に引きつけたもの、叉はこの前後に伊丹へ買い取った新しい伊丹の酒株である。つまり元祿頃には、伊丹の酒造家で十萬石の酒は制限されつヽも造られていたのである。
そして延享元年甲子歳九月の酒造人数帳に見るに、酒株は依然として百参株、徳川末に至るまで十萬石の酒は年々造られている。
さてその頃の酒家にどんなのがあったか、そしてどれ位あったか。
それは正徳五年の二つの株帖に出ている株主名並びに惣連名によって瞭然たるものがある。試みに左に十二月分の惣連名を記載することにしよう。
| |
薬 屋 新右衛門 |
豊島屋 兵右衛門 |
植村屋 庄右衛門 |
| |
丸 屋 甚 兵 衛 |
稻寺屋 弥右衛門 |
升 屋 忠 兵 衛 |
| |
稻寺屋 治郎三郎 |
油 屋 藤右衛門 |
薬 屋 叉右衛門 |
| |
丸 屋 重 兵 衛 |
多田屋 清右衛門 |
大阪屋 兵 助 |
| |
外 屋 三郎右衛門 |
升 屋 宗 兵 衛 |
大鹿屋 伊 兵 衛 |
| |
一文字屋 与治兵衛 |
伊勢村屋 嘉左衛門 |
茶 屋 治郎兵衛 |
| |
油 屋 八郎兵衛 |
かせや 与右衛門 |
堂 屋 八 兵 衛 |
| |
油 屋 勘 四 郎 |
丸 屋 仁 兵 衛 |
豊嶋屋 治郎左衛門 |
| |
丸 屋 重右衛門 |
紙 屋 八左衛門 |
堂 屋 四郎右衛門 |
| |
一文字屋 作左衛門 |
大黒屋 善右衛門 |
丸 屋 七左衛門 |
| |
升 屋 九郎左衛門 |
升 屋 太郎右衛門 |
油 屋 彦 九 郎 |
| |
木綿屋 七郎右衛門 |
松 屋 与 兵 衛 |
薬 屋 兵 四 郎 |
| |
油 屋 勝右衛門 |
升 屋 彦 三 郎 |
大鹿屋 市郎兵衛 |
| |
清水屋 彦 兵 衛 |
稻寺屋 七 兵 衛 |
かせや 伊 兵 衛 |
| |
升 屋 清 兵 衛 |
豊嶋屋 休 甫 |
かせや 忠 三 郎 |
| |
大鹿屋 叉 三 郎 |
大鹿屋 忠 兵 衛 |
豊嶋屋 半 兵 衛 |
| |
一文字屋 助五郎 |
丸 屋 喜 兵 衛 |
一文字屋 七兵衛 |
| |
稻寺屋 四郎兵衛 |
同 町 三右衛門 |
薬 屋 与 市 郎 |
| |
丸 屋 八郎右衛門 |
西 屋 忠 兵 衛 |
稻寺屋 彦四郎 |
| |
升 屋 佐 兵 衛 |
油 屋 源 兵 衛 |
升 屋 徳 兵 衛 |
| |
一文字屋 助三郎 |
大阪屋 四郎五郎 |
かせや 与治右衛門 |
| |
かせや 忠左衛門 |
大鹿屋 藤 兵 衛 |
大鹿屋 五右衛門 |
| |
桑名屋 吉 兵 衛 |
油 屋 三郎兵衛 |
|
これ等酒家の主人は、花車豪宕な生活をしていたもので、風流を解するものが極めて多かった。例えば上記連名中の油屋勘四郎は姓を上嶋といい俳人青人であり、彼の有名な鬼貫もその同族で油屋一門に俳士多く、その江戸酒肆の番頭に至るまで(俳人文海)俳諧を嗜んでいる。更に一文字屋与治兵衛が俳人好昌であり、新町丸屋仁兵衛が鷺助である等高名の俳人は枚挙に遑がない。 |
|