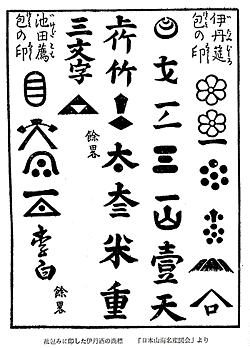
菰包みに印した伊丹酒の商標 「日本山海名産図会」より
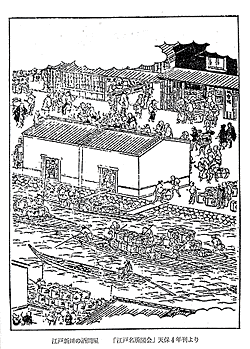
江戸新川の酒問屋 「江戸名所図会」天保4年刊より |
各酒造家は各々自家独特の酒銘を持っていた。それも一つや二つでなく然も年を経るにつれて次第に増加している。それを酒樽を包む菰巻の外に大きく記入して(酒印叉は菰印とも呼ぶ)店叉は得意先に送ったものである。一家の沢山な印を用意していたことは、得意先によって異にしたり、製造法によって区別したりすることもあったと思われる。
この酒銘は所謂商標権利があったので模造したり、勝手に使用したりすることは出来ない。即ち始めて作ったり借用したり相続したり売買したりする時は、その都度々々届け出たものと見える。
旧伊丹酒造組合所蔵の印帳は、酒銘の所謂登記簿の様なもので、極近年の幕末頃のものまで記入されているがこの中にある鹿島や茂兵衛の商標は 白鹿    等が載っている。(鹿島や清太郎と茂兵衛は同一家である)叉この印帳の初めの方に載っているのは古いもので正徳の油屋の顔ぶれが見える。例えば八尾八左衛門は紙屋八左衛門であり、小西新右衛門は薬屋新右衛門、上嶋八郎兵衛は油屋八郎兵衛、柄谷庄右衛門は植松庄右衛門である。紙屋八左衛門の菊印は彼の松江維舟の句 等が載っている。(鹿島や清太郎と茂兵衛は同一家である)叉この印帳の初めの方に載っているのは古いもので正徳の油屋の顔ぶれが見える。例えば八尾八左衛門は紙屋八左衛門であり、小西新右衛門は薬屋新右衛門、上嶋八郎兵衛は油屋八郎兵衛、柄谷庄右衛門は植松庄右衛門である。紙屋八左衛門の菊印は彼の松江維舟の句
伊丹こそ菊の元船江戸廻し
に読まれているところで、最も古いものヽ一つとして有名である。
叉薬屋の  、白雪、庄右衛門の 、白雪、庄右衛門の 、油屋の三文字なども古くから知られている。尚この印帖によると、上述の鹿清の白鹿を始め山本庄兵衛の男山、大関等現今灘方面に使用されている酒印の少なからず含まれているのを見る。これ等はその印が当地の酒に本源を持った証左である。 、油屋の三文字なども古くから知られている。尚この印帖によると、上述の鹿清の白鹿を始め山本庄兵衛の男山、大関等現今灘方面に使用されている酒印の少なからず含まれているのを見る。これ等はその印が当地の酒に本源を持った証左である。
この頃の伊丹酒の品質はどうであったか。それはいうまでも無く天下の絶品である。で伊丹酒がよく販れた原因は、上述の近衛家の特別の寵庇によるのであるが、独りそれのみというわけでない、其品質が芳醇無比よく当時満天下の愛飲家を魅了礼賛、随喜の涙を流さしたということに負う所も亦頗る多かった。天与の恵、伊丹の井水の酒に適った事は言うまでもないが、中には東を流れる猪名川の水を汲んで酒に用いた向もある(これは池田郷で専ら行われていたところである)この特殊製造によった酒には なる焼印を用いていた。(焼印とは、菰巻の酒印の肩に焼いて捺した印をいう)叉一文字屋では箕面山頭の瀑水を以て酒を醸し、その銘を滝水といったと逸士伝は記している。それから なる焼印を用いていた。(焼印とは、菰巻の酒印の肩に焼いて捺した印をいう)叉一文字屋では箕面山頭の瀑水を以て酒を醸し、その銘を滝水といったと逸士伝は記している。それから という焼印をも捺したのもある。これは米を吟味したことを表現するもので、三嶋郡粟生村の産米を用いるというのである。粟生村は現今に至るもモト米産地を以て知らされている。そしてこの頃の伊丹酒が果してどれ位の価格で江戸へ売られていたか、上記の有岡年代秘記正徳五年の条を見るに という焼印をも捺したのもある。これは米を吟味したことを表現するもので、三嶋郡粟生村の産米を用いるというのである。粟生村は現今に至るもモト米産地を以て知らされている。そしてこの頃の伊丹酒が果してどれ位の価格で江戸へ売られていたか、上記の有岡年代秘記正徳五年の条を見るに
伊丹酒江戸売口五十二両
と出ている。これは十駄の価格であって、その頃の物価としては余程高価であったと思われる。後の天明七年の記録を参照するに
六月米価二百三十目、酒造高三分一造御国觸七月当郷上酒江戸売口四十六、七両、味淋五十両
とあって、この天明の米高が時の相場より尚高価である。
更に灘酒沿革誌の江戸積の市価寛政参年の條を見るに
| |
伊丹酒 |
三六両三歩 |
| |
池田酒 |
三四両一歩 |
| |
西宮酒 |
三三両二歩 |
| |
堺 酒 |
三三両三歩 |
| |
御影西組酒 |
三 五 両
|
とあって、わが郷土酒断然トップを切り他の追従を許していない。(寛政三年は天明七年から四年後にすぎない)
之等の市価から見ても、わが伊丹酒の品質の無比であったことが窺い知られるであろう。
西鶴著 織留巻一 津の国のかくれ里
「爰に津の国伊丹諸白を作りはじめて家久しく……池田、伊丹の売酒、水より改め米の吟味、麹を惜まずさはりのある女は
蔵に入れず、男も替草履はきて出し入れすれば、軒をならべて今の繁昌、枡屋、丸屋、油屋、山本屋……」云々
に述べているところは、よく当時の実状を示し、その頃の酒家(織留の出版は元祿七年である)が如何に米、水を吟味し細かいところまで注意して吟醸したかを物語っている。この枡屋は上記酒屋名寄せ中の枡屋九郎左衛門(鹿嶋家)であり、丸屋は丸屋甚兵衛(森本家)叉はどの一族、油屋は油屋八郎兵衛、山本屋は池田の山本屋太郎右衛門またはその一族を指しているのである。
黄金ほうだる酒は招くで、徳川中葉の伊丹の町は、時にとっての文士芸術家達の隠れ里であった。俳人であれ、詩人であれ、小説家であれ、伊丹酒の芳香は彼等の心をとらえ蕩かすにあまりにも適していた。中でも特筆されることは頼山陽が竹田、小竹等と常に伊丹に出没滞留して、時の銘酒剣菱の美に蕩酔し
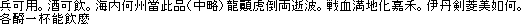
と頼山陽が歌っている「戯作摂州歌」は有名である、叉当時の伊丹酒造家の生活は、大名も三舎を避ける豪奢ぶりであった。その様子は、前掲の「織留」の津の国のかくれ里の節に西鶴が例の迫真力を持つ筆致を以て、仔細に且つ巧みに描出している。そして叉酒屋の力は実に偉大なるものであった。元祿十年十月には酒家年中行司へ惣宿老の称号を被仰付けている。
時代は少し後になるが享和元年八月調の伊丹の軒数は二千百六十七軒で人口八千二百三十七人となっている。徳川中葉も、多く見て恐らく弐千軒余の家数と一万近くの人口ではなかったろうか。そのうちで百軒の酒屋があり、それに附随した出入商人、十万石近かくの米を動かす米屋、年二十万丁からの樽を製造する樽屋、それから竹屋、薪屋、菰屋、運搬問屋並びに諸職人迄を加算すると、町勢の大部分は酒で占め、夢の国にある様子酒の都を構成しておったことが想像される。されば寒造りの最中、伊丹高台から四方の溝渠に向って流れ落ちる水は、文字通りに白化した。これは米を洗ふ汁の流れであり、爰に四囲の田畑はこの肥料によって完全に多収穫が実現されていたということである。叉袋洗いと称して毎酒造期の終りに酒袋を洗滌する、この水は白いのみならずプンと芳醇の香が鼻を衝く。所謂酒精分を多量に含有しているのである、だからそこらの粕汁よりは、この方が余程うまく酔ったと言われている。
賤の女や袋洗の水の色 鬼貫
なる句はこの間の消息を伝えて躍如たるものがある。 |
|