(拲1)乽埳扥偼擔杮忋庰偺巒傔偲傕塢偆傋偟丅偙傟傑偨屆棃媣偟偒偙偲偵偁傜偢丄傕偲偼暥榎宑挿偺崰傛傝婲偰丄峕晎偵攧巒偟偼丄埳扥椬嫿崈抮懞嶳拞巵偺恖側傝丒丒丒乿亀擔杮嶳奀柤嶻恾夛丒姲惌11擭(1799)楺壺偺栘懞寭偐摪岴嫳亁
摉帪偺庰憿傝偼廐偺斵娸夁偓偺乽怴庰乿偐傜丄弴師乽娫庰乿乽姦慜庰乿乽姦庰乿偲巇崬傓偺偑捠忢丅怴庰偼屆暷傪巊偄丄偟偐傕傑偩巆弸偺尩偟偄帪愡側偺偱丄憗偔偱偒傞偑庰幙偼椙偔側偄丅姦憿傝偺姦庰偼嶨嬠傗晠攕嬠偑擖傝偵偔偄搤婫偱丄弮悎攟梴偝傟偨堦斣椙偄庰偲側偮偨丅
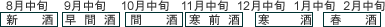
(拲2)暷偺僨儞僾儞傪崓偵傛偮偰摐暘偵曄偊丄偦偺摐暘偵峺曣偑嶌梡偟偰庰惛暘傪嶌傝弌偡偵偼丄峺曣傪弮悎偵偟偐傕戝検偵攟梴偟丄庰曣傪偮偔傝丄偙傟傪?偵巇崬傓憿傝曽丅
乽惗傕偲偼擹岤側惔庰偺忴憿偵揔偟偰偍傝丄挿偄屚傜偟婜娫傕懴偊傞摿惈傪桳偟偰偄傞丅亀撳偺庰梡岅廤傛傝亁乿
(拲3) 崈抮壠揱丒嬽榖(弌揟偼峕屗屻婜偺亀愛梲棊曚廤亁)奣梫儝r丒嶳拞庰揦偺壓抝偑丄庡恖傊偺暊偄偣偵奃傪庰壉偵搳偘崬傫偩丅偦傫側偙偲偼業抦傜偢丄庡恖偑庰傪媯傒忋偘傞偲丄嶐擔傑偱戺偭偰偄偨庰偑偒傟偄偵悷傒丄崄枴傕椙偔側偭偰偄偨丅偙傟偼丄壓抝偑搳偘擖傟偨奃偵傛傞偙偲傪撍偒偲傔丄偦傟埲屻偼奃傪壛偊偰惔悷偵側偭偨庰傪攧傝弌偟偨偲偙傠偙傟偑戝偄偵摉偨偭偰丄屻悽丄晉壠偺戞堦偵側偭偨丅偙傟偲摨椶偺愢榖偼丄峕屗屻婜偺亀婐梀徫棗亁亀杒曯嶨廤亁亀廋嵵嬤娪亁亀楺壺擴晽亁亀崙巎娽亁亀愮擭娪亁側偳偵傕偁傞丅
(拲4)峕屗慜婜偺晜悽憪巕嶌幰丒攐恖丅杮柤暯嶳摗屲丅戝嶃偺恖丅惣嶳廆場偺栧偵擖偭偰択椦晽傪妛傇丅亀岲怓堦戙抝亁亀岲怓堦戝彈亁亀擔杮塱戙憼亁亀惣掃怐棷亁側偳
(拲5)晜悽憪巕丅榋姫丅杒忦抍悈曇丅惣掃偺枹姰惉偺乽杮挬挰恖娪乿偲乽悽偺恖怱乿傪崌傢偣偰丄偦偺杤屻1694擭姧峴丅亀峀帿墤亁
(拲6)悪嬍(偡偓偨傑)偲傕庰()椦(偝偐偽傗偟)偲傕偄偆丅悪偺梩傪懇偹偰捈宎栺係侽噋偺媴忬偵傑偲傔偨傕偺偱丄庰憿壠偱偦偺擭偺怴庰偺偱偒偨偙偲傪抦傜偣傞偨傔偵丄尙偵捿傞偝傟偨傕偺偱丄屻偵庰壆偺娕斅偲傕側偭偨丅)
(拲7)恖栚偵偼怗傟側偄強偵偁傞偲偄偆桾暉側懞棊丅懡偔棟憐嫿丄愬嫬偺堄偵巊偆丅偙偙偼愛捗偺傗傗墱傑偭偨偲強偵偁傝丄嬤悽弶婜偐傜庰憿嬈偱桾暉側挰恖偑懡偐偭偨埳扥傪偝偡丅亀懳栿惣掃慡廤丒惣掃怐棷丒柧帯彂堾亁
(拲8)亀屆帠婰亁偺弌塤恄榖乽戝幹(偍傠偪)戅帯乿偵嫮偄庰(敧墫愜擵庰)偼丄弉惉偟偨傕傠傒傪嶏偭偨廯偵丄壗搙傕尨椏暷傪暘偗偰搳擖偟偰憿傞偲偁傝丄偙偺曽幃傪偄偆丅摨偠曽幃偑亀帊宱亁側偳偵偼乽拺乿朄偲偁傞丅
(拲9)愄偼庰憿傝偼彈惈偺巇帠偲偝傟丄乽搧(偲)帺(偠)乿(晈恖丄彈惈)偑揮偠偰尰嵼偺乽搈巵(偲偆偠)乿(婫愡庰憿岺偺挿)偲側偭偨偲傕偄傢傟偰偄傞丅
(拲10)乽戺庰(偩偔偟傘)乿乽偳傃傠偔乿乽傕傠傒庰乿偲傕偄偄丄敂傪暘棧偟側偄偱丄偦偺傑傑偺庰丅尰嵼偼丄峔憿夵妚摿暿嬫堟朄偵愝偗傜傟偨乽庰惻朄偺摿椺乿偵傛傝丄尷掕偟偨応強偱傒偺憿傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅戺庰偺掕媊偼乽帺傜惗嶻偟偨暷(枖偼敒側偳偺摿掕暔昳)丄暷偙偆偠媦傃悈傪尨椏偲偟偰敭峺偝偣偨傕偺偱丄偙偝側偄傕偺乿偲側偮偰偄傑偡丅
(拲11)姍憅帪戙偵婲偙傝幒挰帪戙偵敪払偟偨嬥梈婡娭丅搚憼傪峔偊偰嬥昳傪偁偢偐傝丄傑偨幙暔傪擺傔偨丅晉桾側庰壆偑暪偣偰塩嬈偟偨傕偺偑懡偄偺偱丄庰壆搚憅偲暪徧丅偳偦偆偲傕塢偆丅亀峀帿墤亁
(拲12)堦斀(360曕)偺暷偺廂妌崅偼丄12乣13悽婭偵偼丄嬤婨偺忋揷偱1愇2搇乣1愇3搇傎偳偵側傝丄偙傟偼8乣9悽婭偵斾傋傟偽丄3妱偐傜6妱偺憹廂偱偁傞丅亀擔杮偺楌巎丂忋亁(堜忋惔丄娾攇怴彂)
(拲13)幒挰帪戙崰偱偼丄怙偼尯暷傪梡偄丄妡暷偵偼敀暷傪梡偄偰偄偨丅塱榎帪戙(1560擭崰)丄擇抜巇崬偐傜嶰抜巇崬庰憿傝偺媄朄偑偐傢傝丄偙傟傪彅敀偲徧偟偨丅峕屗弶婜偵偼丄怙偵尯暷丄妡暷偵敀暷傪梡偄偨傕偺傪曅敀偲徧偟丄偦偺椉曽偵敀暷傪梡偄偨傕偺傪彅敀偲徧偟偰偄偨丅亀撳偺庰丂梡岅廤亁
(拲14)愴崙戝柤偺丄巗偲嵗偺撈愯尃傪斲掕偟丄帺桼塩嬈傪擣傔傞惌嶔偼丄妝巗丒妝嵗偲偄傢傟丄揤暥18擭(1549)丄嬤峕偺嵅乆栘巵偑偦偺椞崙撪偱偍偙側偭偨偺偑嵟弶偲偝傟傞丅亀擔杮偺楌巎丂忋亁(堜忋惔丄娾攇怴彂)
(拲15)揤暥尦擭(1532)丄億儖僩僈儖偺庱搒儕僗儃儞偱惗傑傟傞丅16嵨偱僀僄僘僗夛偺擖夛丅塱榎6擭(1563)棃擔丅屲婨撪偍傛傃嬨廈偱晍嫵偺戞堦慄偱妶桇偟偨屻丄揤惓11擭(1583)丄擔杮暃娗嬫挿偐傜乽擔杮巎乿偺曇弎傪柦偤傜傟傞丅廏媑偺敽揤楢捛曻椷偺屻丄儅僇僆偵戅嫀偟偨偑嵞傃擔杮偵栠傝丄宑挿2擭(1597)丄挿嶈偱杤偡傞丅挿偄晍嫵妶摦傪捠偟丄怣挿偲偺夛尒偼18夞偵偍傛傃丄廏媑傪偼偠傔懡偔偺愴崙晲彨偲偺柺幆傪摼偨丅亀姰栿丂僼儘僀僗擔杮巎丂拞岞暥屔亁(昅幰徯夘傛傝)
(拲16)偁傞擭丄埳扥偺憏廻榁偺傕偲傊撏偄偨彂忬偵乽埳扥偼庰憿娞梫偺抧偱偁傞丅傛偦傛傝庰偺抣抜偑憡楎偭偰偼丄悐旝偺婎偱偁傞丅憿庰偺媀偼丄偦偺擭偺帪岓偵傆偝傢偟偄昳幙偺傕偺傪偮偔傞傛偆丅傒偩傝偵慹埆偺庰傪憿傝丄廬棃偺埵丄奿傪庢傝幐傢側偒傛偆偝傟偨偄丅庰壠偲傕偳傕丄偮偹偯偹怺偔怱摼怽偡傋偟乿偲偁偮偨丅亀媨悈暔岅
撳屲嫿偺楌巎丒撉攧怴暦嶃恄巟嬊曇亁
(拲17)亀愛捗嵼嫿挰偺揥奐亅埳扥傪拞怱偲偟偰尒偨傞亅丒拞晹傛偟巕亁傛傝
(拲18)庰憿姅偲偼丄奺庰憿壠偺庰憿暷崅傪姅崅偲偟丄偙偺姅崅偲偲傕偵庰憿恖偺嫃強偲柤慜傪昞帵偟偰奺帺偵岎晅偟偨娪嶥偱偁傞丅偙偺姅嶥偺強桳幰偵尷傝庰憿偑擣傔傜傟丄偟偐傕姅崅埲忋偺庰憿偼嬛巭偝傟偰偄偨丅枊晎偺庰憿摑惂偼偙偺庰憿姅崅偵傛偭偰幚巤偝傟偨丅亀埳扥庰憿嬈偲彫惣壠丂巎椏偵尒傞嬤悽埳扥庰憿嬈丒愇愳摴巕亁傛傝
(拲19)枊晎偼朙嶌偲暷壙掅棊傪攚宨偵庰憿彠椼嶔傪偲傝丄乽尦榎廫塏擭擵掕悢枠幰怴庰姦憿彑庤師戞偨傞傋偟乿偲晍崘偟偰丄愊嬌揑偵庰憿彠椼傊偲惌嶔傪揮姺偡傞偺偱偁傞丅亀擔杮庰惻朄巎丂忋丂壞栚暥梇亁丂乽枊弶埲棃偺嵼曽庰憿嬛巭惌嶔傕庛傑傝丄塩嬈摿尃偲偟偰偺庰憿姅偺忳搉攧攦偑帺桼偲側傝丄庰憿嬈偦傟帺懱偵嫞憟宊婡偑摫擖偝傟偰偔傞偺偱偁傞丅亀嬤悽撳庰宱嵪巎丒桵栘妛亁
(拲20)揤曐11擭(1840)嶳梂懢嵍塹栧偑敪尒丅庰憿偵揔偟偨椙幙偺庰憿梡悈偱惣媨巗撪偺摿掕偺抧壓偐傜媯傒忋偘傜傟偰偄傞堜屗悈丅
(拲21)傕傠傒偺巇崬悈偺偙偲傪媯悈偲偄偆丅撳庰偼埳扥庰偵斾偟偰丄巊梡悈検偑懡偔丄廫悈(偲傒偢)懄偪忲暷10愇偵懳偟悈10愇偲側傝丄偄備傞乽墑傃偺偒偔乿庰偲側偭偨丅
(拲22)戝惓枛婜偵庰憿傝梕婍偲偟偰嚅噱堷偒揝惢偺忴憿梡僞儞僋偑奐敪偝傟傞丅
(拲23)
(1) 亀楺懍偺晽亁埨惌擭娫丄戝嶃挰曭峴媣恵旤桽惽乽崑壠崈抮慞塃塹栧愭慶丄岺晇偟偰弶傔偰惔庰傪惢偟弌偣傝丄乧乿
(2) 亀愛梲孮択亁尦榎侾係擭乮侾俈侽侾乯壀揷宬巙丂埳扥庰偼乽埳扥懞偺巗揦偵憿傝丄恄嶈偺墂偵憲傝丄彅崙偺(3) 捗偵弌偡丄崄枴恟旤偵偟偰丄怺偔庰傪岲恖枴擵丄摉強偺庰偲抦傞帠丄懠偵彑傞屘栫乿
(4) 亀愛捗柤強恾夛亁乽柤嶻埳扥庰丄庰彔偺壠俇侽梋屗偁傝丄傒側旤庰悢愮愇傪憿傝偰彅崙偵塣憲偡丅摿偵偼丄嬛棤挷峷偺柫庰傪榁徏偲徧偟偰嶳杮巵偵偰憿傞丅偁傞偄偼晉巑敀愥柤庰偼摏堜乮彫惣乯偵偰憿傞丅乧乿
(5) 亀榓娍嶰嵥恾夛亁惓摽係擭乮侾俈侾係乯帥搰椙埨曇嶽乽摉悽忴偡傞庰偼丄怴庰丄娫庰丄姦慜庰丒姦庰摍側傝丄廇拞怴庰偼埳扥傪柤暔偲偟偰乧乿
(6) 亀枩嬥嶻嬈戃亁侾俈俁俀擭乽憏偠偰峕屗偵偰偼丄堦愗抧憿傝偺庰偼側偟丄帪偲偟偰崱斏壺偺峕屗丄偄偔敧昐敧廫傗傜傫丄曽検柍曈偺懘強偵丄擔栭挬曢偵偮偐傆庰丄懡偔偼傒側塃偵偄傊傞埳扥晉揷丄偁傞偄偼抮揷偺壓傝庰側傝乿
(7) 亀奀棨摴弴擔婰亁乽擔杮拞僿庰儝憿儕弌僗抮揷丒偄偨傒乮埳扥乯僩僥丄寢峔僫儖庰僲弌儖搚抧僫儖儓僔乿
亀栄悂憪亁姲塱侾俆擭乮侾俇俁俉乯徏峕廳棅丄亀擔杮塱戙憼亁掑嫕係擭乮侾俇俉俈乯丄亀杮挬愄晽懎亁堜尨惣掃丄亀崱媨偺怱拞亁曮塱俈擭乮侾俈侾侽乯嬤徏栧嵍塹栧丄亀晽懎暥慖亁尦榎枛婜攎徳偺栧恖怷愳嫋榋丄側偳偵傕嫇偘傜傟偨傝戣嵽偵傕側偭偰偄傞丅
(8) 埳扥庰偺拞偺乽寱旽乿偑丄尦暥俆擭乮侾俈係侽乯偵彨孯偺屼慜庰偵慖偽傟丄乽扥忟乿偼棅嶳梲乮侾俈俉侽乣侾俉俁俀乯偑徧巀偺帿傪巆偡丅傑偨埳扥庰偼枊晎偺姱梡庰偲偟偰乽屼柶庰乿傪柤忔傞偙偲偺偱偒偨戝庤俀係尙偵偼懷搧偑嫋偝傟丄懷搧屼柶偺庰壆偼乽屼庰壆乮偍傫偝偐傗乯乿偲曭傜傟丄暲偺庰壆偲嬫暿偝傟偨丅
(9) 亀愛梲懕棊曚廤亁乽埳扥丒抮揷偺憿傝庰偼彅敀偲偄傆丅尦棃悈偺傢偞偵傗丄憿傝偨傞帪偼丄庰偺婥恟偩偐傜偔丄乧乿

